株式会社グローバル・プランニングの代表取締役の金賢守(キムヒョンス)と申します。
今回は日本の年金制度について調べてみました。
日本の年金制度は高齢化社会に対応するために幾度も改正されてきましたが、その中で特に年金支給年齢の引き上げと年金金額の調整について記事を書いていきます。
年金支給年齢の推移
1959年に国民年金法が施行された当初、年金支給開始年齢は55歳でした。
その後、1986年の改正で国民年金の支給開始年齢が60歳に引き上げられました。
厚生年金についても1994年の改正で支給開始年齢を段階的に60歳から65歳へと引き上げることが決定されました。
2013年から2025年にかけて、実際にこの引き上げが行われている最中です。
現在、少子高齢化と長寿化により、さらに支給開始年齢を引き上げる議論が進行中です。
将来的には、支給開始年齢が70歳にまで引き上げられる可能性もあります。
これは平均年齢や健康寿命が伸びているので単純に年金の制度が長期に渡って国民に年金を支給できる設計になっていないため必然的な流れだと思います。
年金額の推移
年金額は、経済状況や賃金、物価の変動に応じて調整されてきました。
高度経済成長期には経済の拡大とともに年金積立金も増加し、年金額も上昇しました。
しかし、1990年代初頭のバブル崩壊後、経済の低迷とともに年金財政も厳しくなり、給付水準の見直しが行われました。
2004年には、年金額を抑制するための「マクロ経済スライド」制度が導入されました。
この制度により、物価や賃金の伸びに応じて年金額が自動的に調整される仕組みとなり、年金額の増加が抑制されるようになりました。
現在、国民年金の月平均支給額は56,479円と、この制度の影響を受けて5年前の55,615円より実質的に増加が緩やかになっています。
結論
年金支給年齢の引き上げと年金額の変動は、持続可能な年金制度を維持するための不可避の措置です。
これにより、現役世代の負担を軽減し、長寿化社会に対応しています。
個人は、これらの変化に対応するために早期からの自分の年収に応じた資産形成やライフプラン、今後のキャリアの見直しが求められています。
出典
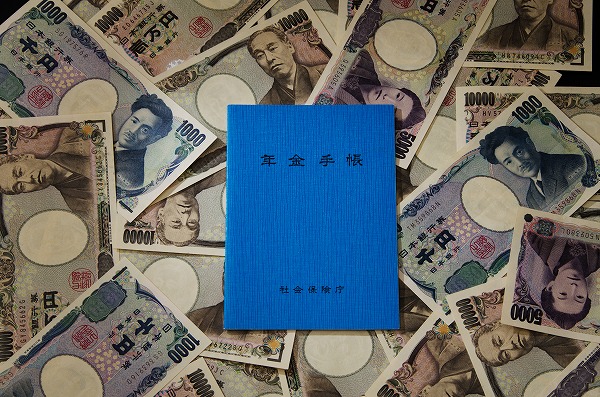


コメント